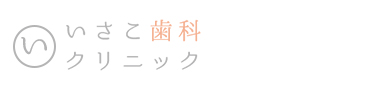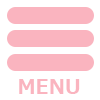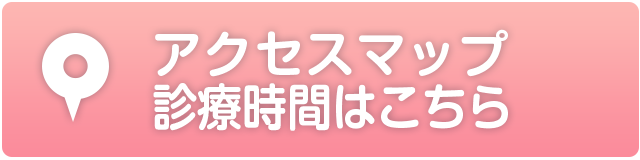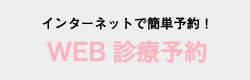開院のお知らせ
2019年1月1日(火)新規開院
◯◯駅エリアに新規開院するビスカデンタルクリニックです。
むし歯・歯周病はもちろん、インプラントや矯正などの専門的な治療もお任せください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
内覧会のお知らせ
開院に先がけて院内を見学いただける内覧会を開催いたします。
ご予約不要ですのでお気軽にお越しください。
◯月◯日(◯)…00:00~00:00
◯月◯日(◯)…00:00~00:00
◯月◯日(◯)…00:00~00:00

カウンセリング重視・
インフォームドコンセントの
徹底
歯科医院で、「いきなり歯を削られた」「治療の説明をきちんとしてもらえなかった」などの不安な思いをされたことはありませんか。当クリニックでは、治療の流れ・治療期間・治療費用について、最初に明確にご説明します。患者様にご納得いただいた上で治療を進めてまいりますので、気になることがございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。

患者様を待たせない・
全ての診察室は完全個室
当クリニックではできるだけ患者様をお待たせしないために、待合室を設けておりません。
診療室は全て個室の造りになっておりますので、まわりの患者様を気にすることなく治療を受けていただけます。

滅菌の徹底
歯の治療中は、飛び散った唾液や血液が器具に付着します。院内感染を防ぐためには器具の滅菌を徹底することがとても重要です。当クリニックでは器具の滅菌はもちろん、できるだけ使い捨ての用具を使用することで、院内感染防止に努めています。